サマープログラムに参加して
開発政策プログラム 芳山慧子/2015年度 KDISサマープログラムに参加
夏期1ヶ月、韓国セジョン市にあるKDIスクールのサマープログラムに参加した。国際色豊かなKDIスクールにおいては、プログラムに設けられた韓国フィールドトリップや講義、大学生活を通じて、様々な貴重な体験をさせていただいた。
KDIスクールは本年2月ソウル特別市から世宗(セジョン)特別自治市にキャンパスを移設。滞在中は、KDIスクール敷地内に併設された学生寮で生活した。新設されたばかりの校舎、研究施設は最新のシステムが導入されており、セキュリティカードを使用することで24時間出入りが可能である。数多くの学生が校舎内の学習スペースで土日、また夜遅くまで学習に励んでいた。
世宗特別自治市は、首都ソウルの人口一極集中及び地方との格差の是正を目的とした首都機能移転プロジェクトにおいて、首都として新たに整備されたまちである。当初計画では大統領府、国会、中央官庁すべてを移転させる予定であったが、その後中央官庁のみを移転させる計画へと変更され、現在まで徐々に整備・移転が進められている。至る所で住宅、公共施設等がまさに建設中であり、わずか1ヶ月の滞在の間においてもバスルートやバス停の位置・名称が変わるなど、新しく発展しつつあるまちの姿を目の当たりにすることができた。
現在の日本においては、このような国家規模のプロジェクトの決定、推進が行われることは少ないが、戦後の総合開発計画のようにかつては格差是正や一極集中解消、地方振興という観点から様々なプロジェクトが実施されてきた。今回の韓国訪問を通じ、「国土の発展」を考えた場合、これらのテーマはどの国にとっても重要な命題であるということを感じた。
私は海外留学や生活の経験がなく、韓国への渡航も初めてであったためサマープログラムへの参加は大変緊張していた。しかし、KDIスクール、GRIPSのスタッフそして多くの留学生の助けを得て安心して過ごすことできた。GRIPSにも海外から多くの留学生が来ているが、KDIスクールで出会った留学生との交流における最大の違いは、「相手は日本のことをほとんど知らない」という点である。日本の国土、人、経済、習慣、文化、社会システム、福祉、歴史など、「日本人として」容赦なく質問を浴びせられたが、これらについて正しく実態を伝えられるだけの知識すら持ち合わせていないことを実感した。海外に住むということは、その国についてのみならず自国について考えることのできる貴重な機会であると思う。私たちはどのように違うのか、そして何故違うのか、何を共有するのか。グローバル・コミュニケーションという言葉が人口に膾炙するようになって久しいが、その本質は決して言語ではない。今回の体験を通じ、グローバル・コミュニケーションの難しさを改めて認識した。
世界を感じる貴重な経験
開発政策プログラム 下村史郎/2015年度 KDISサマープログラムに参加
KDIスクール2015サマープログラムに参加し、様々な国からの留学生と知り合う機会を得た。大学の講義だけでなく、食事や観光を共にし、彼らと会話をすることで、世界の人々について知り、世界を感じることができた経験は大きい。
2週間にわたるOECDに関する講義では、国家の発展や経済の成長に対する、彼らの積極的な発言に驚いた。彼らには自国の発展を目指した大局的なものの考え方があることを改めて認識した。その下に地域の人々の暮らしや考え方があるのだ。地域の事項を考える上でも、国家の成長を見据えた大局的な見地から、人々のニーズを見極めていくことが重要であると思った。ディスカッションでは、人前で発言することが苦手な日本人に対し、諸外国の人たちは、自分の意見を持ち、はっきりと意見を述べるという点において、大きな違いを感じた。
静岡県の職員である私は、常に地域の人々のことを考えていて、世界の人々にまで目を向けることはほぼなかった。しかし今回の留学生との交流によって視野が広がったと感じる。研修を通じて発見したことや、知り合った様々な国の友人たちは、私の新たな財産である。
サマープログラムで学んだこと
地域政策プログラム 平林明日香/2015年度 KDISサマープログラムに参加
第1週目に行われたアサン市、ポハン市、キョンジュ市等を巡る現地視察でまず気づかされたのは、隣国である韓国について私自身、これまでわずかな知識しか持っていなかったということである。
ここでは経済分野に話を絞るが、これまでの韓国の経済発展の道程が日本と酷似しているという点には強く興味をひかれた。このような状況は両国が共通しておかれている環境及び文化に起因しており、これが今日における産業構造の類似につながっている。
この環境とは両国のおける自然資源に乏しい状況であり、これにより製造業での技術の向上に注力せざるを得ない状況にあった。また文化的な面でも双方とも中国から大きな影響を受けていたことから近似する部分が多く、労働者の仕事に対する考え方や働き方についても似ていると感じる場面が多くあった。
このように、両国とも製造業が中心となって経済を牽引していき、日本で言えば車産業、韓国で言えば家電産業が世界で大きなシェアを占めるまで発展していくことになる。
このような類似性のために、自然と両国が同じ分野での競争的関係になることは当然といえる。その一方で、先進国の役割である世界、特に途上国での貢献を考える際には、協力関係を築く一つの可能性を示唆しているといえる。
次にOECD事務局による講義について振り返る。ここでは3人の講師がそれぞれ異なる分野、「国際間の移民について」、「事業が及ぼす影響の計測について」、「経済発展の先にある『開発・発展』について(GDPを超えて)」について講義を行った。
どれも今日の日本と深く関わる問題であり、新たな知識や視点を得ることができた。中でも「事業が及ぼす影響の計測」に関する講義は興味深く、プロジェクトにおける「評価」の方法について学ぶことができた。
これについて、制限された財政状況の中でどのようにプロジェクトを実施し評価していくかは重要な視点である一方、これが適切に行われているかといえば、多くのプロジェクトで誤った手段が用いられているというのが講師の分析であった。
ここで学んだ評価手法を、私自身が愛知県において関わったプロジェクトに適用して再度考えを深めるよい機会であった。
最後に、現地での留学生との交流について述べる。様々な背景を持った留学生との交流は、文化面や知識面で刺激を受けるのはもちろんであるが、彼らの視点を通じて、日本の現状が世界からどのように受け止められているかという外の視点を得ることができたのはすばらしい経験であった。
例えば、何人かの学生から現在の日本の経済政策である「アベノミクス」について尋ねられた。「アベノミクス」という言葉を知っているだけでも驚いたが、このような意見交換は視点を変えるという意味でも重要であったと感じる。つまり、普段日本に住む限りでは、一人の住民として、または地方公務員としてこの現象を捉えているに過ぎないが、彼らの意見を通して、世界から見てどのように捉えられているか、どのような役割が期待されているのかという見方を学んだのは大きな成果であった。
新しい行政都市で刺激的な研究セミナーを受ける特別な機会
安藤 優香 / 安全保障・国際問題プログラム
2014年度 KDIS短期研修に参加 (2015/3/10-12)
今回の韓国KDISへの訪問には、GRIPSの構成を反映した国際色豊かな学生が参加した。現地では、GRIPS及びKDISの博士課程学生による自身の研究発表が行われ、様々な角度から切り込んだその内容は、双方の学生にとって今後の研究に大いに参考になるものであった。
研究発表に先立ち行われた大山達雄先生の特別講義は、博士論文における統計学、データの使い方や分析の仕方をコンサイスに、分かりやすい事例を参照しつつ紹介し、私のような統計をあまり必要としない博士論文のテーマを検討している学生にとっても、非常に参考になった。両大学の博士課程学生による研究発表も、テーマ設定やアプローチ(データの収集など)を含め、それぞれ得るところが多かった。いずれの発表においても活発な質疑応答があったのは、学生たちの研究意欲を刺激している証左であろう。
KDISは今年ソウルからセジョンに移っており、今回その新しいキャンパスで交流プログラムが実施されたことも大きな目玉であった。韓国政府が主な行政機能をセジョンに移している中、その新しい街の現状を垣間見られた。セミナー終了後、KDISの新キャンパスの見学ツアーがあったが、最新設備の大学院は、韓国の大学院、そして研究機関の未来を見るようで、刺激があった。図書館の在り方など、GRIPSや日本の大学院も参考にできる点が多いのではと感じた。また、研究所(KDI)と大学院が隣り合わせで、相互交流がしやすい環境も効率的であるとの印象を持った。
今回の訪問の良かった点は、参加したGRIPSの学生たちが時間を共有し、日頃できない意見交換を行えたことである。GRIPSのキャンパスでは、クラスで一緒になる以外は、挨拶を交わす程度の交流になりがちであるが、今回の研究発表を端緒にお互いの研究テーマや、関心事項、さらにはそれぞれの出身地に関する話まで、様々なトピックスについて忌憚のない意見交換が出来た。
異文化に触れながらの人的ネットワーク形成と研究交流
松原 治吉郎/ 安全保障・国際問題プログラム
2014年度 KDIS短期研修に参加 (2015/3/10-12)
本研修では、KDIスクールの学生・教授陣とのプレゼンテーション・ディスカッションセッションを通じ、双方のアカデミックな関心事について知見を深めることができた。また、行動を共にした研修参加者との交流を通じ、これまで自らのコース内に限られていた人間関係をそれ以外のところにも広げることができた。更に、フィールドトリップを通じ、韓国の伝統・歴史・文化に触れる機会を持てたことは非常に有意義な経験であった。中でも、ソウル市内の各所で現在の日韓関係を反映する様々な光景を目にしたことは、外交・安全保障を専門とする私にとって、日本にいては得難い実地経験であった。
自分の職務の専門分野を超えて見聞を広めることができ、非常に有意義な機会
高崎 美奈子 / 公共政策プログラム・厚生労働省
原 文絵 / 公共政策プログラム・文部科学省
2014 Global Government Officials Seminar on G20 and Development Policy 参加 (2014/12/6-12/12)
 セミナーには、日本、インド、韓国、中国、ブラジル、インドネシア等のG20諸国のほか、G20の取組みや今後の方向性について学ぶ開発途上国からも多くの政府関係者等が出席しました。
セミナーには、日本、インド、韓国、中国、ブラジル、インドネシア等のG20諸国のほか、G20の取組みや今後の方向性について学ぶ開発途上国からも多くの政府関係者等が出席しました。
最初の二日間は、韓国の大学教授等による講義が行われ、オーストラリアがホスト国となった2014年G20会合における主要議題であった雇用創出、社会保障、ジェンダー、環境問題、途上国への国際協力など、喫緊の政策課題に関する解説がありました。最後に、2015年のトルコでのG20会合のねらいと討議の方向性に関する講義もあり、最新事情を幅広く鳥瞰し身に付けることができました。
相互理解と協力が重要かつ必要であること
衛藤 陽平 / 開発政策プログラム・新21世紀政治経済研究所
清華大学SPPM短期研修参加 (2014/11/24~11/27)
清華大学キャンパスツアーで同大学の規模や歴史、機能をこの目で見て体感することができ、非常に感銘しました。特に図書館や 旧正門などの歴史的建造物は、清華の起源や学問の府としての伝統の厚みを象徴するもので、強い印象を受けました。GRIPSプロモーションでは、同僚の学生がGRIPS の強みにつき熱弁を振るい、清華大学の学生がGRIPSへの留学体験を激賞するのを聞き、私自身GRIPSでの教育のコア・バリューなるものを再認識するに至りました。このプロモーションに続く学生交流会は、今年度前期までGRIPSで勉強していた清華大学SPPMやKDISの学生との再会の場にもなりまして、我々学生世代の友情と日中韓連帯がさらに深まった気がします。
最終日の感謝祭イベントでは、出身国・地域や職業経験の面で様々なバックグラウンドを持つ留学生たちと交流でき知人も増えました。彼らとの会話を通して、清華大学の留学生が、中国が安定的な成長を息長く持続させるために不可欠な政策運営の管理手法やその教訓について非常に熱心かつ貪欲に学んでいることを知り驚きました。
この短期研修で学んだことによって、平和と調和を維持しながら成長し得る社会を実現するためには、リージョナル、そしてグローバルの両方のレベルで、相互理解と協力が重要かつ必要であることを、改めて認識しました。このために、キャンパスアジアの交流プログラムが、各分野における現在そして将来のリーダーたちが、視野を広め、この地域の国々の懸け橋となる幅広い人的ネットワークを確立するうえで、非常に役立っていることは、間違いありません。今回の訪問を含めいくつかのプログラムに参加しましたが、GRIPSの現在の学生にも、将来の学生にも、キャンパスアジアの交流プログラムに参加することを強くお勧めしたいですね。
国の文化の違いや学生生活などあらゆる面に話が及び見識を深めた
鶴井 達也 / まちづくりプログラム・石川県庁
清華大学SPPM短期研修参加 (2014/11/24~11/27)
今回、中国を初めて訪問し、現地での体験の折々で、日本との文化や大学生活の違いなど新しい知見を得る機会になりました。地方自治体の一職員として、その地域内での活動が中心であった自分にとっては、異文化交流はこれまでの自分の価値観や考え方に大きく影響を与えるものになりました。清華大学の学生や職員の方々は英語能力が堪能である方が多く、中国語を耳にする機会は少なかったですが、英語能力を鍛える良い機会を得ましたのも、一つの収穫です。
キャンパスの広大な敷地の中に、学生だけでなく、大学で働く教職員や過去に大学に在籍した教授の家族も居住しており、食堂だけでなくコンサートホールや市場や商店などもあって、敷地の中だけで生活が完結できるほど充実したミニ経済圏が形成されていることに日本との大きな違いを感じました。1905年開校時の建物が残っており、新しい建物との調和が全体としてとれて、風情を感じました。

授業では、銀行を中心として世界の経済事情、中国での農業や交通など最近の状況についての講義を受講しました。授業内容の充実ぶりもさることながら教員と学生との丁丁発止のやりとりが非常に印象的でした。教員への質問が活発に飛び交い学生相互の討論を通じ深みのある授業になっているように感じました。GRIPSの国内プログラムではあまり見慣れない光景であり、学生の意識の高さにカルチャーショックを受けました。また、アフリカを中心にさまざまな国から政府職員を中心に留学生として学んでいるSPPMの学生との交流会を通じて、国の文化の違いや学生生活などあらゆる面に話が及び見識を深めることができました。

 海外の国を単に観光するのではなく、そこに住む人々とのコミュニケーションを深めることで、考えや文化を知ることができ、真の意味でのその国の理解につながることをこのプログラムで痛感しました。最後に、4日間という比較的短期間ではありましたが、今後の学生生活、さらに来年度以降の社会人生活において貴重な財産となる素晴らしいチャンスを与えていただいた派遣元や清華大学とGRIPSの職員の方々、そして参加された両校の学生の皆さま方にも厚く御礼申し上げます。
海外の国を単に観光するのではなく、そこに住む人々とのコミュニケーションを深めることで、考えや文化を知ることができ、真の意味でのその国の理解につながることをこのプログラムで痛感しました。最後に、4日間という比較的短期間ではありましたが、今後の学生生活、さらに来年度以降の社会人生活において貴重な財産となる素晴らしいチャンスを与えていただいた派遣元や清華大学とGRIPSの職員の方々、そして参加された両校の学生の皆さま方にも厚く御礼申し上げます。
語学能力より「オープンな心」
岡部 功 / 開発政策プログラム・清水建設株式会社
清華大学SPPMサマープログラム参加 (2014/8/6~9/4)
私にとって、今回の中国の訪問は初めての経験で、当初イメージしていた中国とは大きく異なるものでした。清華大のサマープログラムの間、中国人学生や職員の方々に学業だけでなく生活の面でも多大なるサポートをして頂きました。クラスメートすべてが中国以外の出身者であり、また中国人学生や職員の方々は英語能力が堪能であるため、中国語を学ぶ事は十分できませんでしたが、その分英語能力を鍛える良い機会を得る事が出来ました。今回は沢山の親切な中国の人々に出会う事ができた事は私にとってかけがえのない経験となりました。江西省の視察においては、スタッフの学生が、私が勤めている会社の歴史まで勉強しており、深いおもてなしの心に感心しました。
一ヶ月間のサマープログラム中の様々な授業に参加する事は、私にとって異文化についての知識を得る貴重な機会となりました。授業中に議論する事を通して、生活、理論から公共政策までのプロセスは国によって、多面な視点と配慮を政策計画に導入させないといけない、という事を学びました。この経験は私の視野を広げるものであり、今後につながると考えています。
最後に、キャンパスアジアプログラム清華大学サマープログラム参加は、私にとって人生の大切な経験で、宝物といっても過言ではありません。今回のサマープログラムを通して、世界の広さを知る事が出来た事、国際的な友情を築く事が出来た事、多くの貴重な経験を得る事が出来た事すべてに心より感謝を申し上げます。この経験はGRIPSの学生の方々にも勧めたいと思っています。事前に英語能力を準備する事はとても大切ですが、コミュニケーションをする上で最も大切な事は、語学能力より「オープンな心」である事を強く感じています。
社会で様々な経験を積んだ学生こそがこのような体験をすべき
木村 祐輔 / 開発政策プログラム・東日本高速道路株式会社
KDISサマープログラム参加 (2014/8/5~9/5)
KDISサマープログラムの講義内容は、非常に興味深くかつ面白い内容でした。特にアフリカ及びラテンアメリカに関する経済状況などを学ぶ講義については、自らの興味・関心の幅を大いに広げさせられました。また、韓国語のビギナーコースについては、語学だけではなく韓国の文化的な側面も学ぶことができ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。
更にこのプログラムに参加してよかった点として、留学生という立ち位置で他国の学生と接する体験ができたということもあります。GRIPSにおいても、留学生と接する機会は多数ありますが、自らも留学生という立ち位置で他国の学生と話をする体験は、日本にいる限り絶対にできないことです。チャンスがあるならば、ぜひとも体験することをお勧めします。

GRIPSの学生の多くは、就業後数年経った学生ばかりですが、社会で様々な経験を積んだ学生こそがこのような体験をすべきであると強く感じています。海外留学というと、通常の大学生など20代前半が対象として語られがちな部分はありますが、ある程度社会に対する自らの見方を持っている年代、つまりはGRIPSの学生こそ、このプログラムに参加するメリットがあるのではないでしょうか。
清華大学短期派遣研修報告
まちづくりログラム 小林健二 / 清華大学短期研修参加 (2013/10/29-11/1)
今回の研修では、清華大学で様々な講義を受けさせて頂いた。その講義の中では、中国の年金と住宅問題について詳しく知ることができた。年金は、農民戸籍と都 市戸籍そして公務員とでそれぞれ格差があり、公務員がかなり優遇され、その格差が問題となっている。また、中国でも急速な高齢化が問題となっており、これ により年金について財源確保の問題を早急に解決しなければならないと、日本と同様な問題を抱えている。また、住宅については農村部や周辺地域から都市部へ の人口の流入により住宅購入価格及び、賃借料が高騰しており、低・中所得者層が賃貸を継続できないため、集団居住を選択せざるを得ないなどの問題が起きて いる。この問題を解決するために中国政府は住宅政策を打ち出す予定であるということだった。
また、貿易に関する講義では、世界の国々の方の意見を聞くことが でき、改めて他国の方の意見を聞くことの重要性を感じた。日本で差異はあるが同じ環境で生活してきた人間と、他の文化、他の環境で過ごしてきた人間では、 やはり感じ方、主張が全く違う。それは、それぞれの国の利益を考えた上での主張で、我々が身勝手であると感じるような意見であったり、世界全体を考えてバ ランス良い貿易をしようという建設的な意見であったりと様々である。その様々な意見に対し簡単に解決策を出すことは困難であるが、意見を言い合いその妥当 性を語り合うことはとても重要であると感じた。自分たちの中で常識であることが他国では非常識であることを知ることがあるように、様々な主張を聞くことは 自分たちの視野を広げることができる。そして妥当性のある主張には真摯にその対応策を考えるようになる。当たり前のことであるが、国際力を高めるというこ とは海外に行って観光をして買い物をするだけでは、培われない。海外の人とのコミュニケーション、その国それぞれの文化の中に入ることが重要である。

研修中に、先日GRIPSを卒業した友人2名と夕食を一緒に食べる機会があった。これは、我々にとって、とても新鮮なことで、改めて世界に友人がいることを 実感できる機会であった。GRIPSで友人を作るということは、大きく言ってしまうと世界と繋がるということである。キャンパス・アジアプログラムで他国 で学ぶということは、さらに世界と繋がる機会を増やしてくれるということである。そして言語の重要性も再認識させてくれる。
3泊4日と短い期間であったが、非常に得るものが多かった。キャンパス・アジアプログラムは様々な経験を与えてくれ、非常に有意義なものであった。このような貴重な機会 を与えていただいたことに心から感謝し、今後多くの学生がキャンパス・アジアプログラムに参加することを期待したい。
韓国の地方自治の現状を学ぶ
地域政策プログラム 小澤剛史 / KDIスクールサマープログラム (2013/08/01-08/31)

ポリシー・プロポーザル作成のための研究活動の一環として、韓国KDIスクールでのサマープログラムに参加できたことは、今後の自分の人生を考える上で、非常に大きな意味を持つものだったと実感しています。
地方自治体の職員として、所属自治体の枠の中での活動が中心であった自分にとっては、1ヶ月にも及ぶ異文化交流は、GRIPSでの学生生活で多少の免疫があったものの、これまでの自分の価値観や考え方に少なからず影響を与えるものでした。英語とハングルのみの言語環境で、各国の政府職員を中心とする当該スクールの外国人学生とともに生活し、フィールド・リサーチや韓国中央公務員教育院(COTI)と共催の「グローパル政府職員セミナー」などを通して、互いの考えを共有する経験は日々刺激的であり、月並みな表現ですが視野が広がる毎日でした。また、公式カリキュラム以外にも、一緒に参加した他自治体職員とともに、各地の自治体を訪問し、担当職員の方へのインタビューも行いました。職員の方から、韓国の地方自治の現状、日本との相違点などを直接聞けたことは、翻って日本の地方自治を考える際の新たな視点を得られたと感じています。なお、当該プログラムを通じて親しくなった外国人学生や韓国の若手キャリア官僚とは、帰国後もSNSなどを通じて交流が続いており、将来的には何らかのコラボレーションを実現することができれば面白いと思っています。
今回のサマープログラムは、修士課程の学生(特に地方自治体職員)であっても、本人の意思があり、参加する環境が整うならば、参加した方がよいプログラムであると思います。仮に、自分のように決して英語力が高いとは言えない学生であっても、強い意志と目標があるならば、参加することを勧めたいと思います。
中国の最先端の政策研究の成果を受講
政策分析プログラム 増田 一八 / 清華大学短期研修 (2012/09/26-09/29)

私は講義及び学生との交流から、清華大学公共政策大学院における教育環境、そして中国の文化を学ぶ事を主な目的にこ
の度の短期研修に参加致しました。これらの目的はこの短期研修を通じて大いに達成することが出来ました。
初日にはチェン教授による"Strategic Management of Public Organization"の講義に参加する機会を頂きました。聴講させて頂いた回のテーマは、私が研究の関心を持つ「発展途上国の公的組織」と深い繋がりのある「組織における汚職の防止、撲滅」に関するものでした。この講義の中では汚職の定義や、汚職が起こる前提条件、解決のアプローチが理論とケーススタディを用いて活発に議論されました。GRIPSの政策分析プログラムでは経済学の理論を用いた政策分析を主に学んでいることもあり、自分の専門外の視点から政策を学ぶ事が出来たことが第一点目の成果でした。また、講義の中で清華大学公共管理学院の学生が講義のテーマに沿って,主体的に自国のケースをプレゼンテーションし、それを受けてクラス内で活発に議論をする雰囲気が日常化している様子が強く印象に残りました。GRIPSにも多くのミッドキャリアの留学生が集約しており、このような姿勢を講義内外で積極的に取り入れることで、我々も学生間のシナジー効果をより得る事が出来ると感じ、大変刺激を受けました。
 経済成長の只中にいる中国で市民の生活水準を感じながら、このような最先端の政策研究の成果を受ける事が出来た事は、今後、自身が開発途上国の経済開発政策の研究を行う上で大変貴重な示唆を頂く事ができました。また、講義の後には清華大学の学生が主催する中国の伝統的な満月を親しむ風習「Luna Party」に参加させて頂き、中国文化に触れることが出来ただけでなく、清華大学の公共管理学院で学ぶ学生の背景や学業への姿勢、目標を伺う事ができ、自身のキャリアを考える上でも大きな刺激となりました。この経験から得た示唆、アイデアや人脈を博士課程やその後の研究に活かすことで、双方の大学、国に貢献させて頂けるように努めさせて頂きます。
経済成長の只中にいる中国で市民の生活水準を感じながら、このような最先端の政策研究の成果を受ける事が出来た事は、今後、自身が開発途上国の経済開発政策の研究を行う上で大変貴重な示唆を頂く事ができました。また、講義の後には清華大学の学生が主催する中国の伝統的な満月を親しむ風習「Luna Party」に参加させて頂き、中国文化に触れることが出来ただけでなく、清華大学の公共管理学院で学ぶ学生の背景や学業への姿勢、目標を伺う事ができ、自身のキャリアを考える上でも大きな刺激となりました。この経験から得た示唆、アイデアや人脈を博士課程やその後の研究に活かすことで、双方の大学、国に貢献させて頂けるように努めさせて頂きます。
海外研修の必要性を感じる
まちづくりプログラム 千代反田 誠 / 清華大学短期研修 (2012/09/26-09/29)
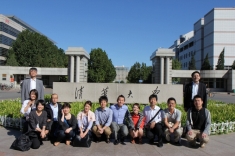 今回の研修で学べたことは、これからの日本人は国際感覚をより培う必要があると感じたことです。GRIPSにも多くの留学生の方がいますが、我々日本人も海外にこれまで以上に目を向けていくことが大切だと痛感しました。そして現地で日本人留学生の方に会い、アメリカなどの英語圏以外の大学にあえて挑戦している姿勢が印象に残りました。
今回の研修で学べたことは、これからの日本人は国際感覚をより培う必要があると感じたことです。GRIPSにも多くの留学生の方がいますが、我々日本人も海外にこれまで以上に目を向けていくことが大切だと痛感しました。そして現地で日本人留学生の方に会い、アメリカなどの英語圏以外の大学にあえて挑戦している姿勢が印象に残りました。
私は今英語の大切さを痛感しています、私はGRIPSに入学して以降英語を聞き取る能力が向上したと感じていますが、今後はより積極的なコミュニケーションを留学生と行っていきたいと考えています。
成長する中国の話はよく話題に上がりますが、やはり現地を見て体験した国の印象は想像以上でした。今回の研修を企画していただいた先生方に感謝致します、このキャンパス・アジアのおかげで貴重な人生経験ができました。また国際情勢が非常に不安定な状況の中での研修運営ありがとうございました。
GRIPS初のキャンパス・アジア奨学生として渡韓
MP2プログラム 尾崎 健人 / KDIスクールサマープログラム (2012/08/07-09/07)
 今回は、GRIPS初のキャンパス・アジア奨学生としてKDIスクール研修に参加した。1ヶ月という長い期間を頂き、KDIスクールの学生と交流を深めるだけでなく、短期の観光客には見えてこない韓国の風土や文化を体験する事が出来た。また、KDIと韓国中央公務員教育院(COTI)が共催した「グローバル政府職員セミナー」にも参加し、韓国の若手キャリア官僚や世界中の政府職員とパーソナルなネットワークを構築することが出来たのは大きな収穫となった。KDIスクールで受講した「開発政策」の集中セミナーにおいては、先進国である日本と韓国がどのように効率的な途上国支援を持続していけるかについて活発な意見交換が行われた。両国がお互いから学べることはまだまだ非常に多いと再確認できた。この様な素晴らしい機会を与えてくれたキャンパス・アジアプログラムに感謝したい。
今回は、GRIPS初のキャンパス・アジア奨学生としてKDIスクール研修に参加した。1ヶ月という長い期間を頂き、KDIスクールの学生と交流を深めるだけでなく、短期の観光客には見えてこない韓国の風土や文化を体験する事が出来た。また、KDIと韓国中央公務員教育院(COTI)が共催した「グローバル政府職員セミナー」にも参加し、韓国の若手キャリア官僚や世界中の政府職員とパーソナルなネットワークを構築することが出来たのは大きな収穫となった。KDIスクールで受講した「開発政策」の集中セミナーにおいては、先進国である日本と韓国がどのように効率的な途上国支援を持続していけるかについて活発な意見交換が行われた。両国がお互いから学べることはまだまだ非常に多いと再確認できた。この様な素晴らしい機会を与えてくれたキャンパス・アジアプログラムに感謝したい。
韓国留学は政策を再考する強いきっかけとなった
政策分析プログラム 大石 陽子 / KDIスクールサマープログラム (2012/08/07-09/07)

短期留学によって私の「日本の外」と向き合う姿勢がこれほどまでに大きく変わるとは予想しなかった。もちろん、限られた時間の中で私たちが見られたものは韓国のごく一部である。それでも、とても内容の濃い留学だった。
フィールドリサーチでは、両国の交流の深さと、共有しているもの多さとを再認識した。一方で、人々の「国家」に対する考え方や「国家と国民との関係」「他人との距離感」といったものと、私が日本で馴染んでいるそれらとの大きな違いも発見した。地理的要因、歩んだ歴史の違い、徴兵制の有無や教育など原因は多々あるが「日本と似ている国」として理解したつもりでいた韓国に、私はより真摯に対峙していく必要があるということを切に感じた。
また、途上国出身の留学生も多いKDI Schoolでは、世界のさまざまな国が「Korea」をどう見ているか感じ取ると同時に、韓国はそれらの国に対してどの側面をアピールしようとしているか、という戦略の一部を垣間見た。韓国の原子力発電所や製鉄会社に留学生たちとともに訪れられたことは貴重な機会だった。
私にとって韓国留学は、日本の果たすべき役割、担える役割や、日本がとるべき政策を再考する強いきっかけになった。このような貴重な機会を与えていただいたことに心から感謝するとともに、より多くの学生がCampus Asia Programを通して留学できればと思う。私にとって有意義な留学であったように、彼らにとっても必ず有意義な経験になると信じている。
視野を広げることで今後の業務に繋がる
地域政策プログラム 仲宗 根睦 / 清華大学短期研修(2012/03/27-29)
 今回の短期研修では清華大学の先生による中国に関する二つの講義を受けましたが、どちらも非常に興味深く、刺激的でした。私は日本の地方自治体職員ですが、講義を聞きながら常に日本の地方自治制度や個人的な業務経験と比較し、講義内容を理解しようとしていたと思います。特に中国の政策運営については、私の知識や経験を超える発想が多くありました。これら講義は純粋な学問というより、私にとってはカルチャーショックを含め既成概念が揺さぶられる経験であり、私個人の中で気づきや新たな疑問が生まれ、視野が広がる貴重な経験でした。地方自治体の業務経験があることや自分の分野を持っているからこそ、さらに強烈な刺激を受けることができたのだと思います。
今回の短期研修では清華大学の先生による中国に関する二つの講義を受けましたが、どちらも非常に興味深く、刺激的でした。私は日本の地方自治体職員ですが、講義を聞きながら常に日本の地方自治制度や個人的な業務経験と比較し、講義内容を理解しようとしていたと思います。特に中国の政策運営については、私の知識や経験を超える発想が多くありました。これら講義は純粋な学問というより、私にとってはカルチャーショックを含め既成概念が揺さぶられる経験であり、私個人の中で気づきや新たな疑問が生まれ、視野が広がる貴重な経験でした。地方自治体の業務経験があることや自分の分野を持っているからこそ、さらに強烈な刺激を受けることができたのだと思います。
KDIスクールで認識した自身の課題
地域政策プログラム 島田 徹 / KDIスクール短期研修(2012/03/13-15)
 KDIスクールの授業を聴講し感じたことは、GRIPSの学生でも十分ついていける内容だということである。今回聴講した授業は主にミクロ経済学であったが、単に理論を説明するだけではなく、理論を説明したうえで、貧しい人に資する政策に結び付けて考えさせるなど、非常に面白いものであった。また学生も熱心に質問しており、学生側のレベルの高さも感じることができた。今回のキャンパス・アジア・プログラムによりダブル・ディグリーや単位互換制度を導入することは、GRIPS学生にとって学習内容もさることながら、学生との交流も深められ、非常に有意義なものになると感じた。 また、自身の課題も感じた。一つは英語力である。授業を完全に理解し、ディスカッションができるレベルとは現在大きな開きがあり、グローバルな活動をしていくためには最も力を入れてレベルアップを図らなくてはならない課題であると痛感した。2点目は研究レベルである。今回GRIPSの博士課程の学生の発表を聞いていたが、内容、発表の技術とも自分のレベルと比べ大きな差があると感じた。もっと研究の質や深さ、発表の技術とも高めていかなくてはならないと感じた。このような課題は今回参加しなければ認識できなかったところであり、これを感じることができたことは大きな収穫であった。
KDIスクールの授業を聴講し感じたことは、GRIPSの学生でも十分ついていける内容だということである。今回聴講した授業は主にミクロ経済学であったが、単に理論を説明するだけではなく、理論を説明したうえで、貧しい人に資する政策に結び付けて考えさせるなど、非常に面白いものであった。また学生も熱心に質問しており、学生側のレベルの高さも感じることができた。今回のキャンパス・アジア・プログラムによりダブル・ディグリーや単位互換制度を導入することは、GRIPS学生にとって学習内容もさることながら、学生との交流も深められ、非常に有意義なものになると感じた。 また、自身の課題も感じた。一つは英語力である。授業を完全に理解し、ディスカッションができるレベルとは現在大きな開きがあり、グローバルな活動をしていくためには最も力を入れてレベルアップを図らなくてはならない課題であると痛感した。2点目は研究レベルである。今回GRIPSの博士課程の学生の発表を聞いていたが、内容、発表の技術とも自分のレベルと比べ大きな差があると感じた。もっと研究の質や深さ、発表の技術とも高めていかなくてはならないと感じた。このような課題は今回参加しなければ認識できなかったところであり、これを感じることができたことは大きな収穫であった。









.jpg)














